気候変動が突きつける危機と、将来への機会
公開日:2025.10.08
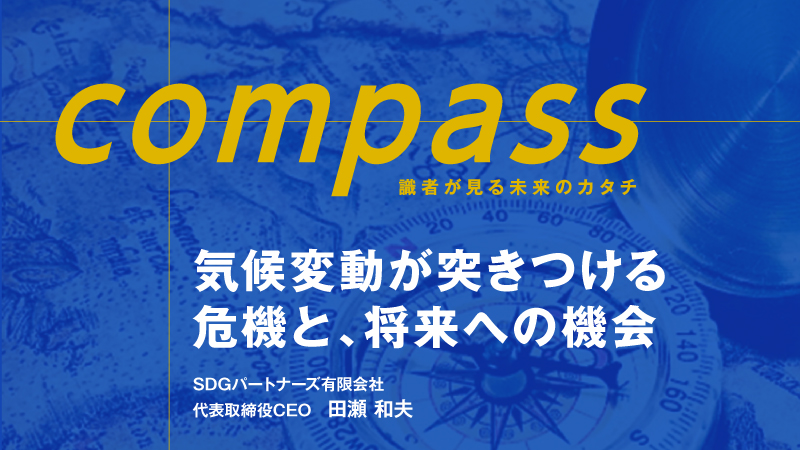
みなさまお元気でしょうか。今年も日本列島は厳しい暑さに包まれ、地域によっては気温が42度近くに達したと聞きます。かつては想像もできなかった数字です。私は7月下旬に松山を訪れる機会を頂きましたが、その日も外気は36度。四国の深い緑、草の匂い、セミの鳴き声に子どもの頃の感覚がよみがえったものの、外に10分もいればくらくらする暑さでした。
人類がホモ・サピエンスとして地球上に現れたのは約30万年前です。長く人口は1万人未満でしたが2000年前頃から徐々に増加し、18世紀半ばの産業革命を境に急加速。指数関数的に増え続け、2022年11月には80億人に達しました。累積人口を約600億人とする説もあり、そうすると人類の10人に1人が今を生きています。この急増は環境負荷を飛躍的に拡大させました。なかでも二酸化炭素の排出は自然の均衡を崩し、大気中に毎年何億トンも蓄積して地球を覆い、熱を逃がさず温暖化を進行させています。1970年代にはその破壊的影響が予測され、1992年の気候変動枠組条約、1997年の京都議定書、2015年のパリ協定など、国際社会は削減に向けた枠組みを整えてきました。ESG投資によるお金も大きく動いています。
それでも温暖化を否定する声は根強く、米国はトランプ政権になって2025年にパリ協定を再び離脱。途上国の中にも経済成長を優先する国があります。しかしIPCC(気候変動に関する政府間パネル)は「人間活動が温暖化の原因であることに疑いはない」と結論づけ、今行動を起こさなければ将来世代に甚大な負の遺産を残すと警告します。
企業にとってTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)対応は人員やコスト負担を伴います。日本では法律で義務化されていないため、中堅・中小企業での取り組みは多くありません。それでも気候変動対策は単なる義務やコンプライアンスを超えた可能性を秘めています。ペロブスカイト太陽電池や全固体電池などの革新は再生可能エネルギーやモビリティの概念を大きく変え、環境と経済合理性を両立させます。技術革新は「市場で勝ちながら環境にも良いことをする」、すなわち「きれいごとで勝つ」戦略の象徴です。規模の大小にかかわらず、企業にとって気候変動は危機であるとともに大きな機会なのです。
今後は気候変動と生物多様性の課題が密接に結びつき、見捨てられている日本の森林や里山が世界的資源となる可能性もあります。短期と長期、利益と社会的インパクトの両立を見据える複眼的な経営こそが、企業と経済の未来を形づくります。国際政治の動向に左右されず、ビジネスが地球温暖化に取り組むべき理由はここにあります。私たちは未来と経済発展の両立に責任を担っているのです。
ともにこの課題に立ち向かいましょう。もちろんちゃんと稼ぎながら。

一覧へ戻る







