【法務編】
賃料増額請求と借主の対応方法
公開日:2025.09.22
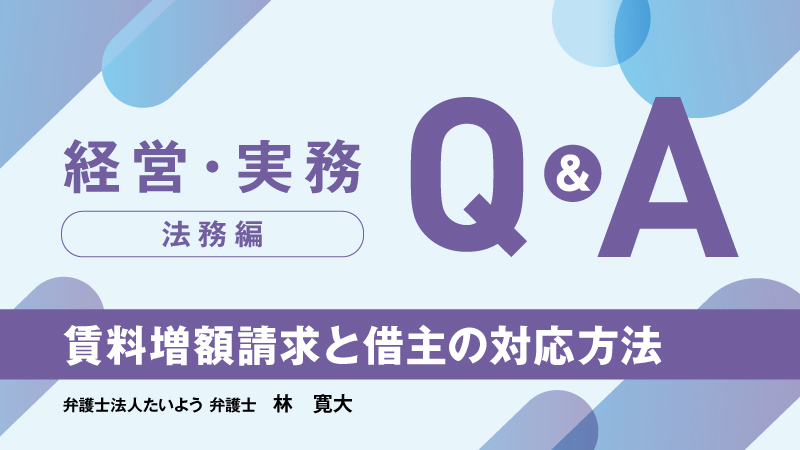
Q. 建物を賃借していますが、貸主から賃料を増額するという通知がありました。どのように対応したらよいでしょうか。
A. 借地借家法により現在の賃料が不相当になっている場合、貸主は賃料を増額できます。現在の賃料が不相当と言える事情があるか、まずは貸主と協議しましょう。
賃料増減額請求権
不動産賃貸借契約における賃料は貸主と借主の合意により決まるのが原則ですが、合意が成立しなくても、一方的に賃料を増減額できる場合があります。それが貸主または借主が賃料増減額請求権を行使する場合で、土地については借地借家法第11条、建物については同法第32条に規定されています。
賃料増減額請求権の行使が認められるのは「建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき」です。
賃料増額請求の効果
貸主が賃料増額請求権を行使した場合であって、現在の賃料が不相当と認められる場合、借主が増額を争ったとしても、その行使の時から賃料が変更となります。例えば、貸主が令和7年9月から5万円の賃料値上を通知して、その値上が妥当だと令和8年1月に決まったとしたら、借主は令和7年9月から毎月5万円の不足額に年1割の利息をつけて支払う必要があります。
不相当の判断材料
現在の賃料が不相当か否か判断する主な事情は次の3つです。
① 土地や建物に対する固定資産税などの税金や、その他の負担が増減したこと
② 土地や建物の価格が上昇・低下したり、その他の経済事情が変動したこと
③ 近隣の同種の建物の賃料と比較して不相当であること
これらの事情はあくまで例示であり、裁判ではその他の事情も総合的に考慮して賃料増額の妥当性を判断します。
借主の対応
協議
借主は、貸主の賃料増額請求を受入れる義務はなく、まずは貸主と協議を行い、増額の根拠や妥当性について話し合います。この協議により、双方が納得できる金額で合意できれば、それが新しい賃料となります。
調停、訴訟
当事者間の協議で解決しない場合、貸主があくまで増額を請求するなら、貸主が法的な手続きを取り、決着をつけることになります。賃料の増減に関する争いは、まず簡易裁判所で調停(話合い)を行い、調停でも合意に至らない場合は、訴訟に移行し、裁判所が最終的な判断を下します。
賃料の供託
増額について合意できない場合、借主は新賃料が決まるまで、増額した賃料の支払いを拒否することができます。ただし、増額を拒否する場合でも、借主は「自分が相当と考える額の賃料」(増額前の賃料など)を支払い続ける必要があります。もし貸主が増額前の賃料の受け取りを拒否した場合は、法務局にその賃料を供託することで、賃料不払いを理由とする契約解除を防ぐことができます。
共益費の増額請求
共益費の増減額について、賃料増減額請求の規定(借地借家法第32条)を準用して、増減を認める判断を示した裁判例があります。当事者間の公平を図るという観点からは、賃料と同様に、共益費についても増減が認められる余地があり、その場合、現在の共益費を決めた当時からの物価や人件費の変動等の事情を考慮して、共益費の増減の可否を判断することになるでしょう。

一覧へ戻る







