【法務編】
中小受託取引適正化法(2026年1月施行)のポイント
公開日:2025.10.31
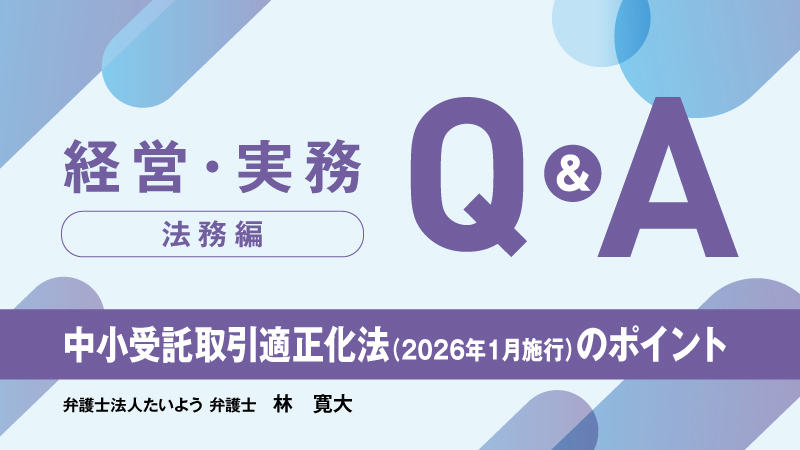
Q. 従来の下請法を改正した中小受託取引適正化法(取適法)のポイントを教えてください。
A. 適用対象の拡大のほか、価格交渉の透明性と取引の公正性を確保するため、禁止行為の追加や事業所轄官庁の権限強化等の大幅改正が行われています。
改正の背景
昭和31年に施行された下請代金支払遅延等防止法(以下、下請法)は、下請代金の支払遅延等を防止することにより、親事業者の下請事業者に対する取引を公正なものとし、下請事業者の利益を保護することを目的としており、長年にわたり中小企業の取引環境を支えてきました。
近年の急激な原材料費や労務費の高騰を背景に、中小企業が適正な価格転嫁を行い、持続的な賃上げを実現させるために、中小受託取引適正化法(以下、取適法)に大幅改正されました。
サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させるためには、協議に応じない一方的な価格決定行為など、価格転嫁を阻害し、下請事業者に負担を押しつける商慣習を一掃していく対応が含まれています。
本稿では主な改正点にのみ触れますが、適正取引の実現のためには改正点以外を把握しておくことも重要です。公正取引委員会ホームページ( https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu.html)で取適法の全容を確認することをお勧めします。
改正のポイント
法律名と用語の変更
法律名が「下請代金支払遅延等防止法」から「中小受託取引適正化法」に変更されただけではなく、「下請代金」が「製造委託等代金」、「親事業者」が「委託事業者」、「下請事業者」が「中小受託事業者」へ用語変更されました。従来の上下関係を払拭し、対等な取引関係を強調するものです。
適用対象の拡大
適用対象となる事業者の基準に、従来の資本金額等による基準に加えて、新たに従業員数による基準が追加されました。具体的には、従業員数300人(役務提供委託等は100人)の区分が新設され、規制及び保護の対象が拡充されます。
また、適用対象となる取引に、特定運送委託(製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託)が追加されました。これにより、発荷主が運送事業者に委託する取引も保護の対象となり、荷待ち・荷役の無償強要などの不当行為に対する抑止力が期待されます。
協議に応じない一方的な代金決定の禁止
製造委託等代金の額に関する協議に応じないことや、協議において必要な説明又は情報の提供をしないことによる、一方的な製造委託等代金の額の決定が禁止されます。例えば、中小受託事業者の代金値上の協議申し入れに対する無視や回答遅延、委託事業者による具体的な理由説明や根拠資料の提供のない代金引下げが、違反行為として想定されます。
手形払等の禁止
製造委託等代金の支払手段について、手形払が禁止されます。また、電子記録債権や一括決済方式などのうち、支払期日までに製造委託等代金の額に相当する額の金銭を得ることが困難なものも禁止されます。
執行強化
事業所轄省庁において、取適法に基づく指導及び助言ができるようになったほか、中小受託事業者が違反事実を情報提供しやすい環境を確保するため、執行機関に申し出たことを理由とする不利益な取扱いが禁止(報復措置の禁止)されます。違反事実の情報提供先として、公正取引委員会及び中小企業庁に加え、事業所轄官庁が追加されます。

一覧へ戻る







